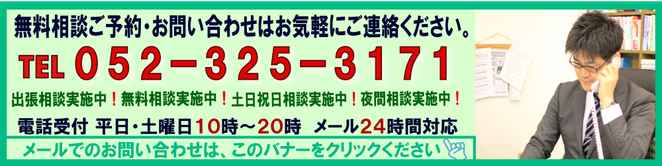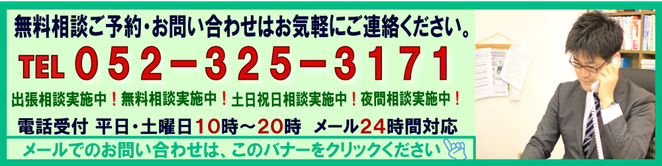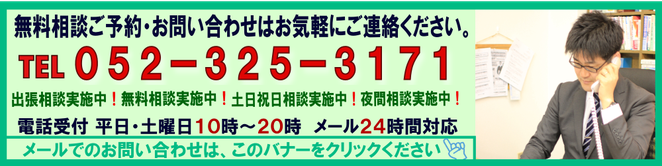遺言書は名古屋の司法書士なごやかにご相談ください
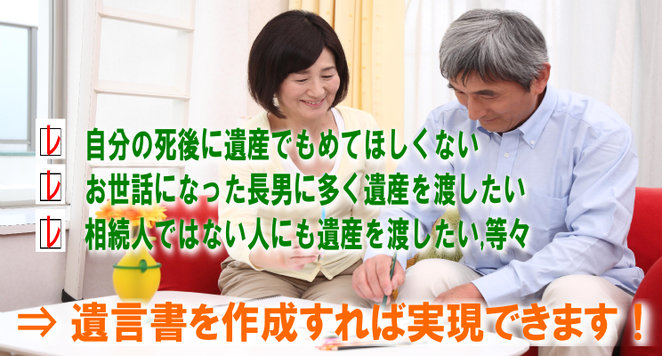

私は遺言書さえ作成していれば、相続が発生した際、こんなにもめなかったという事例を何度も見てきました。
親が遺言書を作成していなかったばかりに、子供である兄弟姉妹が親の死をきっかけに骨肉の争いをするということは想像以上に多いです。当事務所の相談者にも兄弟姉妹や親族との仲が非常に悪くってしまっているケースも多いです。
まさか自分達の子供が争うことはないと思うかもしれませんが、目の前にもらえるかもしれない財産(金銭、不動産等)があるのであれば、もらえるものはもらいたいというのが人間の本性なのです。
このような場合、親がきちっと【遺言書】で子供達への想いを伝えることができれば相続財産をめぐる争いはかなり減らすことができます。
遺言書について相談することや遺言書を作成することに抵抗があったり、不安を感じたりすることがあると思いますが、当事務所は事務所名どおり和やかな相談しやすい雰囲気ですので、雑談しに来るくらいの感じで気楽にご相談いただければと思います。
相談はご家族からの相談でも可能です。この場合、最終的な遺言書作成日までに遺言者本人の意思確認をさせていただきます。
当事務所は名古屋市西区に位置し、遺言書の作成について、名古屋及び名古屋市近郊の方に多数のご相談をいただいていますので、安心してお問い合わせください。
遺言書はいつ作成すればいいですか?

遺言書というと、どうしても死期が近づいてきたときに書くものと思われています。
しかし、いざ死期が近づいてきたときに遺言書を作成しようと思っても、病状が急速に悪化してしまったり、精神的に落ち込んでしまってそれどころではなくなってしまう可能性が高いです。
仮に亡くなる直前に遺言書が作成したとしても、相続人の一部から死ぬ間際に作成された遺言書は正常な判断能力で書いたものではないと無効を主張してくる可能性もあります。
ですから遺言書はお元気なうちに作成していただきたいのです。「いつか作ればいいだろう。」では遅すぎるのです。最近では若い方でも遺言書を作成するケースが増えてきています。
遺言書は一度作成すると、気持ちが変わっても撤回や変更ができないと思われている方がいるかもしれませんが、遺言書は何度でも撤回も変更もできますのでご安心ください。
今後、安心して暮らすためにも、お早めに遺言書を作成することをお勧めします。
遺言書があればできること
・遺産の分割方法を指定できますので相続人の遺産分割協議を不要にできます。
⇒その結果、子供達の相続争いを防ぐことができます。
・法定相続分と異なる相続分の指定ができます。
・相続人以外でお世話になった方にも財産を渡すことができます。
・財産を寄付することができます。
・子供の認知をすることができます。
・財産を渡したくない相続人は廃除することができます。
・遺言執行をしてもらいたい人を決めておくことができます。
・子供たちへの想いを書いておくことができます。
絶対に遺言書を作成してほしい10のケース

特に遺言書を作成すべきケースは下記のとおりです。
下記の場合、遺言書を作成することにより遺言者の希望を実現させることができますし、相続人同士の争いを防ぐことができます。
なおかつスムーズに相続手続きを行うことで、相続人となる方の負担も軽減することができます。
1.別れた前妻との間に子供がいる場合
離婚した前妻との間に産まれた子供は、どんなに疎遠であっても相続人となります。そのため再婚後の妻や子供と前妻の子供が相続人になるケースがあります。
この場合、遺言書が無いと、後妻及びその子供と前妻の子供が遺産分割協議をしなければならなくなります。
後妻及びこの子供はほとんど話したこともない前妻の子供との遺産分割協議は避けたいと思うのが通常なので、このようなケースでは絶対に遺言書を作成しましょう。
このケースが当事務所の遺言書作成の相談で一番多いです。
2.相続人である子供たちに相続争いをしてほしくない場合
自分の子供たちに限って相続争いなんてしないだろうと思っているかもしれませんが、仲の良かった子供達が相続を境に仲が悪くなることは非常に多いです。
子供達に相続争いをしてほしくなくいつまでも仲良くしてほしいと思うのであれば、遺言書を書いて子供達にその気持ちを伝えましょう。
3.特定の相続人に多めに財産を渡したい場合
もし遺言書がなければ、法律で定められた割合で相続することになります。妻が2分の1、子供が2人いればそれぞれ4分の1という感じです。
この割合でなく、例えば子供のうち面倒をよく見てくれた弟に財産を多めに渡したい場合、お墓の管理等ご先祖様の供養を今後していってくれるだろう子供に財産を多めに渡したい場合、事業の跡継ぎに多めに財産を渡したい場合、遺言書に記載しておけば可能になります。
ただし遺留分を侵害する内容になると後でもめる可能性がでてきますので注意が必要です。
4.相続人がいない場合
相続人が一人もいない場合、財産は国のものになってしまします。
せっかく自分が築いた財産が、自分の意思とは全く関係なく全て国のものになるのはもったいない感じがします。
この場合遺言書に財産を渡したい人がいればその旨記載すればその人に渡すことができますし、ご自身が応援したい活動をする団体があれば遺言書にその旨記載すれば死後にその団体に寄付することができます。
5.子供、両親がいなく兄弟姉妹が相続人の場合
子供、親がいなく相続人が兄弟姉妹だけの場合、兄弟姉妹には遺留分が無いので、遺言者は遺言さえ書いておけば好きなように財産を渡すことができます。
例えば兄にだけ財産を渡して弟には一切財産を渡さないということが可能です。財産をもらえなかった兄弟姉妹がいても遺留分減殺請求できません。
逆に遺言書が無いと兄弟姉妹で相続争いになるケースが多いです。兄弟姉妹からの相続は棚からぼた餅的なもので、もらえるものは欲しいという気持ちになるからだろうと思われます。
6.相続人がたくさんいる場合
相続人がたくさんいる場合は、話合いが難航しもめる可能性も高くなりますので遺言書がかなり有効になってきます。
7.内縁の妻及び婚外子がいる場合
内縁の妻や婚外子がいる場合、本妻やその子供も交えての話し合いが困難になることが多いですし、もめる可能性も極めて高くなります。絶対に遺言書があったほうがいい思われるケースの一つです。
8.相続人以外の人に財産を渡したい場合
相続人以外の人に遺贈すると遺言書の中に記載しておけば相続財産を相続人以外の人に渡すことができます。例えばお世話になった方や相続人ではない孫や兄弟姉妹に財産を渡したい場合、遺言書が必要となります。
9.相続人の中に認知症の方がいる場合
認知症の人がいる場合、遺産分割協議をすぐにできなく、成年後見人の選任をした上で遺産分割協議をしなければならないため相続手続にかなりの時間がかかってしまいます。
遺言書があれば遺産分割協議をすることなく相続手続が可能ですので、この場合でもスムーズに相続手続できます。
10.相続人の中に行方不明者がいる場合
行方不明者がいる場合、遺産分割協議をすぐにできなく、失踪宣告の手続き、不在者財産管理人の選任をした上で遺産分割協議をしなければならないため相続手続にかなりの時間がかかってしまいます。
遺言書があれば遺産分割協議をすることなく相続手続が可能ですので、この場合でもスムーズに相続手続できます。
遺言書でもめないための5つのポイント
当事務所では下記のポイントに気を付けながら遺言書の作成のサポートをさせていただきます。
※ただし遺言者の意向により下記のポイントとは異なる遺言書を作成する場合もあります。
1.公正証書遺言を作成します。 ⇒公正証書遺言
2.他の相続人の遺留分を侵害しないようにします。
3.財産を共有で取得することは避けます。
4.相続税が発生しそうな場合は、納税資金対策も検討します。
5.付言事項によりなぜこの内容の遺言書にしたのか遺言者の想いを載せます。
※相続争いを防ぐためには、相続財産、相続人の状況、特別受益、寄与分、遺留分等色々と検討しなければなりませんので、遺言書を作成する際は、専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。
相続税が発生しそうな場合、税理士を紹介することも可能です
3000万円+600万円×相続人の人数の金額を越える相続財産が予想される場合、相続税が発生する可能性がありますので、ご希望があれば相続税に詳しい税理士を紹介することも可能です。
事前に相続税のことも考慮したうえで遺言書を作成しなければならないケースもありますので、その際はお知らせいたします。
遺留分とは?
遺留分とは被相続人(死亡した者)の財産のうち、兄弟姉妹を除く相続人が最低限確保できる相続財産に対する割合のことです。遺留分の割合は、被相続人の直系尊属(父母)のみが相続人のときは直系尊属(父母)全員で遺産の3分の1、その他の場合は2分の1です。
【すべての財産を長男に相続させたい】という相談を受けたりしますが、このような遺言は他の相続人の遺留分を侵害することになってしまします。
遺留分を侵害された相続人は、遺留分を侵害した者に対し遺留分減殺請求をすることができ、その結果せっかく遺言書を書いたにもかかわらず相続人がもめてしまうことがあるのです。
遺言書作成の手続の流れ
1.お問い合わせ・無料相談予約

遺言書、遺言書作成の相談は無料で承っておりますので、まずはお気軽にお問合せください。
最初の相談時では、遺言者本人ではなくご家族の方の相談でも大丈夫です。
まだ遺言書を作成するかどうか決めていないけど遺言とはどんなものか話だけ聞きたいというお問い合わせも大歓迎です。

2.遺言書の無料相談

まずは事務所にお越しいただいて無料相談させていただきます。名古屋及び名古屋市近郊の方に関しては出張相談をすることも可能です。予約いただければ、土日祝日相談、夜間相談もさせていただきます。
遺言書を作成する動機、遺言書に記載する財産、相続人についてお聞きします。
ご依頼いただいた場合は、遺言書作成手続を開始します。

3.相続人調査・相続財産調査

相続人の確認、遺言者の財産の確認をします。この確認をしっかりしておかないとせっかく遺言書を作成してももめる可能性がでてきてしまいます。同時に必要書類の取得もします。

4.遺言書案の作成・依頼者の確認
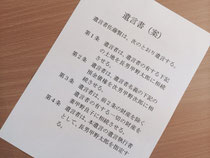
まずはお聞きした内容、打ち合わせした内容を基にして遺言書案を作成し、ご提案します。
遺言書案を確認してもらい、修正、変更をし、納得していただくまで何度でも修正、変更します。
遺言書案の修正や変更を何度しても追加の費用はかかりませんのでご安心ください。

5.公証役場との打ち合わせ(公正証書遺言の場合)

公証役場との打ち合わせが全て当事務所が行いますのでお客様のお手を煩わせることはありません。
具体的には、遺言書の内容、必要書類、公正証書遺言作成の日程の打ち合わせまで全て当事務所で行います。
名古屋の公証役場には名古屋駅前公証役場、葵町公証役場、熱田公証役場があります。

5.遺言書完成

公正証書遺言の場合、公証役場に来ていただいて完成となります。
※公証人が出張することも可能ですが、公証人に払う金額が高くなります。
自筆証書遺言の場合、遺言書案を基にご自身で書いていただき完成となります。
相談から遺言書完成までの期間の目安
2週間から1か月
お客様の遺言書案の検討に時間がかかれば、その分遺言書完成までの時間は長くなります。
遺言書作成の費用
| 手続き | 報酬 |
| 自筆証書遺言作成 |
金4万9000円 (税込 金5万3900円) |
| 自筆証書遺言のチェック |
金2万0000円 (税込 金2万2000円) |
| 公正証書遺言作成 |
金5万9000円 (税込 金6万4900円) |
| 証人立会(2名分) |
金2万000円 (税込 金2万2000円) |
※財産の金額や遺言書の内容や相談回数によっては報酬が変わる場合がありますので、事前にお見積りいたします。
公正証書遺言を作成する場合の実費
自筆証書遺言の場合は遺言を書く紙及び遺言書をしまう封筒さえあれば作成できます。
公正証書遺言の場合は公証役場に下記手数料を支払います。
| 目的の価額 | 手数料 |
| 100万円以下 | 5000円 |
| 100万円を超え200万円以内 | 7000円 |
| 200万円を超え500万円以内 | 11000円 |
| 500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
| 1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
| 3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
| 5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
| 1億円を超え3億円以下 |
43000円に5000万円ごとに13000円加算 |
|
3億円を超え10億円以下 |
95000円に5000万円ごとに11000円加算 |
| 10億円を超える場合 |
249000円に5000万円ごとに8000円加算 |
全体の財産が1億円未満のときは、遺言加算として、1万1000円が加算されます。
祭祀主宰者の指定は、相続または遺贈とは別個の法律行為であり、その手数料は1万1000円とされています。
遺言書作成の必要書類(公正証書遺言の場合)
・遺言者本人の印鑑証明書
・財産を相続させる推定相続人との続柄が分かる戸籍謄本
・財産を遺贈する相手の住民票又は法人の登記事項証明書
・財産を特定するための資料
不動産の登記事項証明書
固定資産評価証明書又は課税明細書
通帳の写し等
・証人予定者の氏名、住所、生年月日及び職業のメモ
・遺言執行者の氏名、住所、生年月日及び職業のメモ
※遺言者が高齢の場合、医師の診断書が要求される場合もあります。
当事務所が遺言書作成で選ばれる5つの理由
1.遺言書の相談は何度でも無料です。
相談料がかかると気軽に相談できないと思いますが、当事務所では無料相談を実施しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。遺言書の相談は初回に限らず、何度でも無料です。
2.遺言書の相談は土日祝日相談、夜間相談を実施しています。
土日祝日相談を実施しております。平日の昼間は仕事で、相談したくても相談できないという声をお聞きしまして夜間の相談も実施しています。ご予約いただければ、夜7時でも、夜8時でも、夜9時でも、夜10時からでも相談可能です。
3.遺言書に関しては出張相談を実施しています。
ご高齢で体が動かないお客様、忙しくて事務所に来ることができないお客様や事務所まで来るのが面倒なお客様のために遺言書の出張相談を実施しています。ご予約時にお申し付けください。※出張相談は名古屋及び名古屋市近郊の方のご相談に限ります。
4.他士業とのネットワークがあります。
弁護士、税理士とのネットワークがありますので、相続争いが生じている場合や税金の相談にも対応できますので、相談時に何でもご相談ください。
5.遺言作成後のアフターフォローもお任せください。
遺言書の作り直しの相談にも対応します。
遺言執行も対応できます。
相続発生時の各種名義変更の相談にも対応します。
遺言書作成のご依頼者様の声
子供達が将来争わないように
名古屋市西区 60代男性

そんなに財産があるわけではないのですが、子どもたちが将来争わないように遺言書の作成をしました。ありがとうございました。
分かりやすく教えてくれました
名古屋市中村区 70代男性

法律のことは全然わかりませんでしたが、佐藤先生が遺言書のことを分かりやすく教えてくれました。今後もよろしくお願いします。